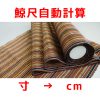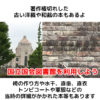見ただけでは素材がわからない物もあるので、館内の職員さんに質問してもいいですかと尋ねたら学芸員さんを呼んでくださいました
この方が色々教えてくださいました!
素材の話をしていたら、催し物の衣装だから当時の威信をかけて絹で作ってるけど、実際は麻だったと思う衣装もあるとのこと。
あと、時代装束の素材で麻って書かれていてるものも
現代人の想像する、リネンやラミーではなくて
その土地で取れた植物の繊維全般の事を引っくるめて麻と呼んでいた
だから当時の服は2代3代かけてようやく着心地が良くなるようなゴワゴワで色も染まりにくく今みたいに沢山なかったと思うよというはなしを聞かせていただきました。
ちなみにファッション美術館ではドレスとかの型紙を販売していて(縮小したものでしたが)
海外のドレスの製図本とか本の通りに作っても同じ形にならないことありますよねという話をしたら有名デザイナーの型紙でも実際のパターンと違うことはあるあるらしいです。
ファッション美術館には現在1万点の貴重な衣装があるそうなんですが
ドレスとかは数千万出せば復元が出来るが難しいのは下着っていってました
当時のものをちゃんと復元しようとしたらクリノリンとかパニエは億かかっても作れないかもしれないとおっしゃっていました
下着は残らないからだそうです。
リンドバーグ城で発見された下着とかとても貴重なのでしょうね
日本語でのまとめ
そんな写真から私が暇つぶしに3Dに起こしてみたのがこれ
当日は当然展示物に触ってはいけないので、床にはいつくばって裏を覗き込んだりしてましたw
意外だったのは綿が一般に流通し始めたのは結構あとの時代だそうで
帰宅して調べたら江戸時代くらいという記事を見ました
戦国時代まではまだ輸入品で貴族のものだったようです。
洗濯しても落ちない染料は最近になってからのようですが
織りの技術はすごいですね
こんな時代からもう機織でこんなに綺麗な柄を織りで作り出せたの!?と愕然としました。
浜田さんいわく、はるか昔の人間も今の教育をすれば、同じように育っていたと思う
だから布は縦糸と横糸の織りの組合せだけでいろんな柄が作れるのだから
複雑な織り模様も作れる人もいただろうとのこと。
ただ染料は天然の動植物の汁とかだから洗濯したら色落ちがすごかったんだろうなあ
ほんとすごく面白かったです。
日本衣装絵巻―卑弥呼から篤姫の時代までは2016年1月までの特別展示なので、興味がある方は早めに行くのをオススメします(o^-^o)
常設展示のドレスもすごかったですよ
ナポレオンの戴冠式の衣装は当時実際に製作に関わった工房に依頼して製作したそうです
6年がかり?といっていたでしょうか。
金モール刺繍?厚みがすごいです
何匹刺繍したんだっていう位の蜂の刺繍
いったいいくらかかったんでしょう、戴冠式の服なので恐ろしい金額なんでしょう。
あとドレスのパターン、布に収まらなかったのか左右のそでで形が違っていたり、縦横が違ってたりするんですって。
本物を採寸して、再現する際に、貴重な衣装を解くわけにはいかないので、隠れたヒダなどをどうやって採寸したかというと
布に同じ柄をプリントして同じように柄が出るようにして調べたのだそうです。
私のような個人ではとても出来ない、さすが美術舘の仕事です。
ただ見るだけという受身だと得られる情報は少ないですが
何か勉強して帰ろう、自分の身にして帰ろうと思っていくとぜんぜん違うので、洋裁を勉強している人は、ぜひ行ってみてください
関連ページ