横に1.5倍以上伸びる生地で作るブーツカバーの型紙の作り方と縫い方です。
前中心をまっすぐに左右対称で作るので縫い目が入りません。
ただしつま先まで伸ばした形で作るので、足首を90度に曲げた通常の立ち方をすると足首の所に横にしわが入ります。

意外と簡単!ブーツカバーの型紙の作り方
自分の足にラップを巻いて直接ブーツカバーの型紙を作る方法です
いるもの
横に1.5倍以上伸びるニット生地。
レジロンのニット糸
ニット針
7mm幅前後の平たいゴム。
型紙を作る紙、メンディングテープ、シャーペン

作りたい足のサイズを測ってください。
左右対称になるように作るので、B、D、F、Gは測った長さを2で割る。
Gはつま先から8cm位上の甲の部分を測る(靴の裏は測らない)
A~Gまでの数値をメモしてください。


Aの上端から直角にBcm線を引く。

上端からCcm下の所から直角にDcm線を引く。

Ccmの所からコンパスの要領でFcmの弧を書く。
下の所からもコンパスの要領でEcmの弧を書く。
交わった所に向かって線を引いて交わらせる。

下から8cmの所から直角にGcm線を引く。

Gの右端から図のように線をつなぐ。

上で引いた線にと、縦の線に対して直角に補助線を引く。

こんな感じに引いた線の端を通るように線をつなぐ。
直角の補助線は1cm程度端をなぞったら、後は補助線から外れてもかまいません。


左右対称にして縫い代をつける。
上下は3cm横は1cm縫い代をつける。
縫い方
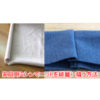
家庭用ミシンでニットを綺麗に縫う方法
ニットってロックミシンがないと縫えないんじゃないの?そういうイメージの方も多いんじゃないでしょうか?
家庭用ミシンでカットソーが縫えちゃう。ニット縫いの基本をまとめてみました
ニット生地は伸びるので写しづらかったり食い込みやすかったりします。
↑上記のページにニットで失敗しにくくなる、綺麗に縫うコツをまとめているので先に見てから縫ってください。


表同士が内側になるように折る。
1㎝幅で縫う。
下側をゴム入れ口として1.5cm開けておく。

縫い代を左右に広げる。
広げた縫い代が閉じないように、下から1.5cmの所で四角く縫う。

上は3cm、下は1.5cmで裏に折る。
上端から2.5cm、下は1cmの所を縫う。
下側にゴムを入れる。

底の縫い代は裏に少し折り込ませて、ゴムがきつくなりすぎない程度まで引っ張って端を結ぶか縫ってつなげる。
つま先がパカパカ浮きそうであれば靴底に当たる部分にゴムを縫い付けておく。

意外と簡単!ブーツカバーの型紙の作り方
自分の足にラップを巻いて直接ブーツカバーの型紙を作る方法です

【おさいほう】男装用ブーツの改造
このアイディア天才や!と思ってご本人に許可を頂いたのでご紹介します。
よくどうなってるの!?っ...

